報告:最適化研究会講演会(名古屋)
- 開催日時
- 2025年2月18日(火)/14:30~16:45
- 会 場
ウィンクあいち(9階905室)およびZoomによるオンライン配信
- 参加者数
- 25名(講師2名含む)
今年度の講演会は、最適化研究会定例会のテーマの中から関心の高かったカーボンニュートラルに向けた取り組みと、温暖地域での地中熱ヒートポンプ利用についてご講演頂きました。
「業務分野のカーボンニュートラルに向けた技術開発」
金岩 勇樹 氏(東邦ガスエナジーエンジニアリング)
東邦ガスのカーボンニュートラルに向けた取り組みについてご講演いただきました。CO2をメタンに変換して活用するメタネーションについて、知多市と連携し、バイオガス由来のCO2からe-メタンの製造実証を開始しています。e-メタンの製造には「サバティエ反応」という、CO2と水素から触媒を介してメタンを生成する方法を利用しています。CO2の分離回収についてはLNG未利用冷熱を利用した回収技術を開発しました。従来の加熱再生方式では加熱用のエネルギーが必要でしたが、減圧再生方式に変更し、未利用冷熱による昇華を利用することで少量のエネルギーでCO2を分離・回収可能となりました。水素燃焼については専用の燃焼バーナーを開発しました。バーナーの排ガス再循環部の配管径を大きくして排ガス循環量を増加させることで、NOx発生量、燃焼効率、燃焼性、耐久性いずれも都市ガス仕様と同等の性能を実現しました。また、CGSで都市ガスと水素を混焼させる場合に、水素の流量制御により混焼率を35%まで向上しました。
「温暖地域における地中熱利用ヒートポンプシステムの最適運転制御」
吉永 美香 教授(名城大学)
温暖地域における地中熱利用ヒートポンプについてご講演いただきました。地中熱利用ヒートポンプ(GSHP)は寒冷地域で発展してきましたが、日本の温暖地域において空気熱源ヒートポンプ(ASHP)と並列に設置される事例が増加しつつあります。一つの事例として、名古屋市の大学施設に導入されたASHPとGSHP+氷蓄熱のシステムを取り上げます。定格能力比はGSHP:ASHP≒1:10、空調負荷特性は冷房負荷:暖房負荷≒2:1です。GSHPを優先稼働させた4年間の実績では地中への放熱量が採熱量を上回り、地温が上昇した結果、年間のSCOPはGSHPの冷2.7、暖3.1よりもASHPのほうが冷暖3.7と高くなりました。GSHPのSCOPが低いのは井水ポンプやボアホールの循環ポンプといった搬送用電力の消費量が多いことやGSHPそのものの効率が低いことに起因します。GSHP利用の最適化を図るため、氷蓄熱を削除、GSHPのCOPをASHPと同等に変更、ボアホール量を2倍にしてシミュレーションを行いました。結果、GSHPを優先的に運転し続けたケースではASHP単独運転時のSCOPと同等となりましたが、地中温度は+0.3℃/年で上昇しました。この問題の解決のため、放熱量が採熱量を超えない制御を実施しました。加えて外気が指定温度を超えた際にGSHPを稼働する制御を導入するとSCOPが約5.3と高くなることを確認しました。
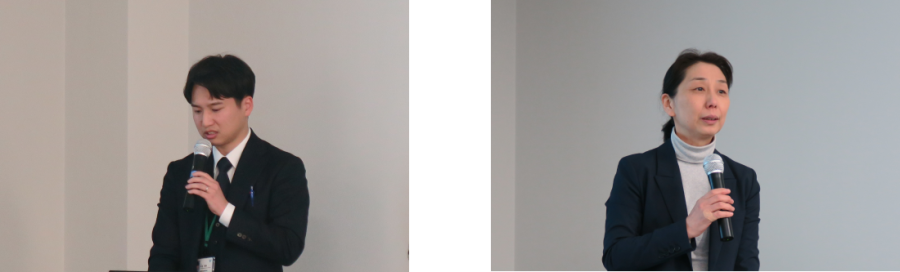
文責:小林
